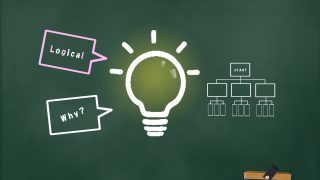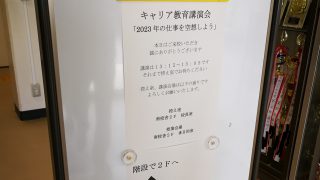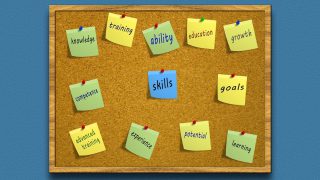私の息子は小学校4年生のときに、聴覚情報処理障害(LiD/APD)と診断を受けました
(2025.4月現在 中学1年)
診断を受けてまもなく3年経ちますが、そもそもどうやって診断に至ったかを書こうと思います。
きっかけは登校渋り
4年生になった5月GW明けくらいのある日、お腹が痛いといって休む日がありました。
それまでも何度か行きしぶりはあり、実を言うと3年生まで朝途中まで登校に付き添って行っていたタイプだったため、お腹は痛くはなさそうだけど、と思いつつその日は休ませて、午後は元気になり、もともと予約していた眼科へ。
眼科を待っている間「今日お休みしたかった本当の理由を教えて」と聴いたところ、驚きの返答が返ってきました。
「(国語で)メモが取れない…」
上記の返答が返ってきたのです。
4年生の国語の5月の学習単元に「聞き取りメモのくふう」という単元があります。
その授業が本人にとってはかなり難しかったようで、休みたかった。とのこと。
なぜその話からAPDに行き着いたか?
ちょうどその頃、以前より気になっていた、息子の「漢字が著しく書けない」ことから、スクールカウンセラーに相談をしていました(この話も別で書こうと思います)。
その時に「視覚認知」という言葉を聞き、視覚の認知機能があるなら、聴覚にもあるのでは?と思ったことがきっかけです。
そこで調べてみたところ、
「声掛けへの反応が遅く、他の子を見てから行動している」
「口頭の指示が通りにくい。忘れる」
「賑やかなところが苦手」
など、数々の特徴が過去も含めて息子にビンゴだったのです。
診てもらえる病院は少ない!
3年前はまだ今ほどこの特性が知られておらず、耳鼻科のDr.も知らないことはザラでした。なので診てもらえる病院は当時もかなり少なかったです。
幸い我が家は、そう遠くない病院で2週間後くらいに診てもらうことができました。
そして結果は、APDと診断されました。
その半年~1年後くらいにはTVなどでも知られるようになりましたが、病院は今も少なく、予約はかなり取りにくいようです。
ですので気になったら、診断が必須でないなら、病院で診てもらうよりも、自治体に相談して受給者証を取得して、療育施設で具体的な手立てを相談しても良いかなと思います。
先生にとっては「さもないこと」 でも子どもにとっては…
やや余談ですが、ちょうどその頃、仕事していた療育施設に元教員の方がいたので、その単元がどれくらい続くのか聴いてみたところ
「そんな単元あったかな…??」とという反応。(苦笑)
調べたところ、2~3回くらいの単元のようです。
もちろんその先生を責めているわけではなく、それくらい先生にとっても、大多数の子どもたちにも「大した単元」ではないけれど、それができなくて困っている子、できるけどものすごーーーくがんばってやっとできるような子どももいる、ということを忘れてはならないと思っています。